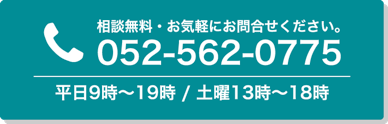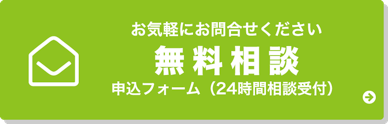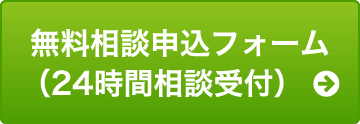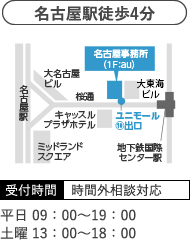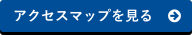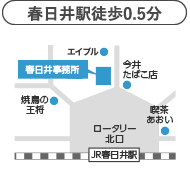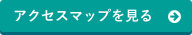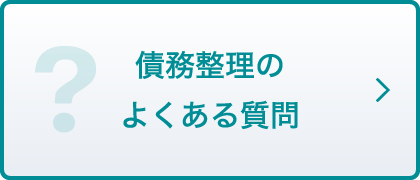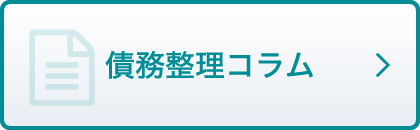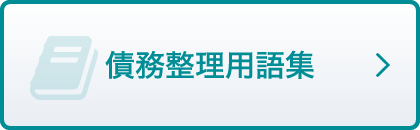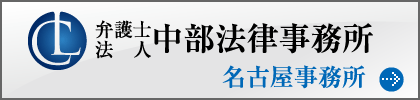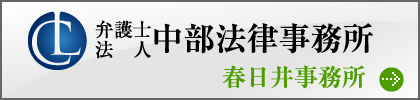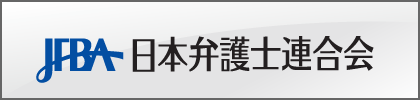回答
個人再生では、原則として財産を処分する必要はありません。ただし、ローンが残っている所有権留保付き自動車等は、通常、債権者に引き揚げられることになります。
また、高額の財産を所有している場合、清算価値保障原則により、最低弁済額が高くなる可能性があります。最低弁済額を3年ないし5年の分割で支払えないときは、一部財産を換価し、再生計画の返済原資にすることも検討する必要があります。
解説
1.個人再生と所有財産の処分の要否
個人再生は、自己破産と異なり、原則として財産を処分する必要はありません。
ただし、個人再生は、任意整理と異なり、すべての債権者を対象にする必要があります。そのため、ローンが残っている所有権留保付き自動車等は、通常、債権者に引き揚げられることになります。
2.住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
前述のとおり、個人再生では、すべての債権者を対象にする必要があります。
しかし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンだけは再生計画による減免の対象から除外することが認められています。これにより、住宅を処分せずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
3.高額の財産を所有している場合
清算価値保障原則(→用語集にリンク)により、再生計画における返済金額の総額は、この清算価値(⇒清算価値とは)より高くなるようにしなければなりません。
預貯金、株式、保険の解約返戻金、自動車など、高額の財産を所有しており、その価値が再生債権総額(住宅ローン以外の借金の総額)に対する最低弁済基準額(借金の総額の原則5分の1)を超える場合、この価値(清算価値)が個人再生における最低弁済額となります。
例えば、借金が600万円の場合、再生債権総額に対する最低弁済基準額は120万円となりますが、200万円相当の財産を所有している場合、200万円(清算価値)が個人再生における最低弁済額となります。
個人再生では、最低弁済額(清算価値が最低弁済基準額を超える場合は清算価値相当額)を、原則として3年(延長されて5年)で分割払いしなければなりません。
しかし、この最低弁済額を3年ないし5年の分割では払いきれない場合は、一部財産を処分して現金に換え、再生計画の返済原資にすることも検討しなければなりません。